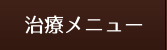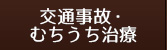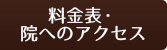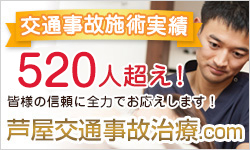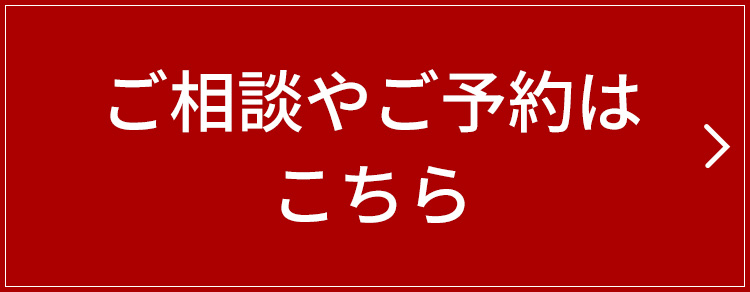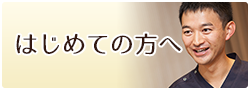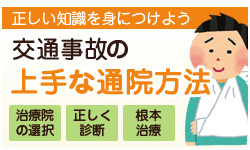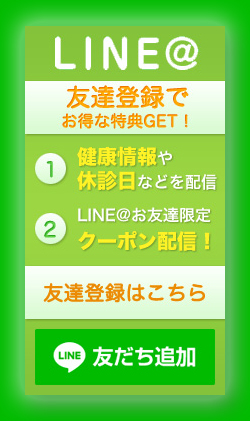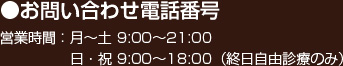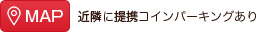手首の腱鞘炎の治し方は?発症の原因や日常生活に与える影響
手首や指に痛みを感じたら、それは腱鞘炎かもしれません。腱鞘炎は、適切な治療を受けないと慢性化してしまう厄介な疾患です。
今回は、腱鞘炎の症状や原因、日常生活への影響について解説します。また、あしや鍼灸接骨院での治療法もご紹介しますので、お悩みの方はぜひ参考にしてください。
腱鞘炎とは
腱鞘炎は、手の使いすぎにより指や手首の関節に痛みが生じる疾患です。手の腱は、指を曲げる屈筋腱と伸ばす伸筋腱に分けられ、それらが腱鞘というトンネルのなかを滑走しています。過度の使用により、腱と腱鞘の間で摩擦が起こり、炎症を引き起こすのです。
さらに、炎症が進行すると腱がひっかかり、指が縮んだばねのように開かなくなる現象が起きることもあります。これが「ばね指」と呼ばれるゆえんです。
腱鞘炎の症状
腱鞘炎の代表的な症状は、手のひら側の痛みです。特に指の付け根に痛みを伴うことが多く、親指、中指、薬指に多く見られます。重症になると、自力で指を伸ばすことが困難になります。
また、指を伸ばす側の腱鞘炎もあります。親指の付け根に生じるドケルバン病がその代表例で、親指を他の指で握った状態で小指側に手首を曲げると痛みが出るのが特徴です。
腱鞘炎の原因
腱鞘炎の主な原因は、手の使いすぎです。パソコンの長時間使用やスマートフォンの操作、家事や育児など、日常生活のなかで手に負担がかかる動作が多いことが発症の背景にあります。
また、手や指の使い方に問題がある場合も、腱鞘炎を引き起こしやすくなります。例えば、ペンを握る力が強すぎたり、キーボードを叩くように打ったりすると、腱に過度な負担がかかってしまうのです。
腱鞘炎が日常生活に与える影響とは
腱鞘炎は、日常生活に大きな支障をきたす疾患です。具体的には、以下のような影響が考えられます。
| ・子供を抱っこできない ・PC作業がはかどらない ・家事が思いどおりにできない ・趣味のスポーツを楽しめない ・スマートフォンの操作が辛い |
このように、腱鞘炎は生活のあらゆる場面で支障をきたします。痛みのために仕事や家事の効率が下がるだけでなく、育児や趣味までも制限されてしまうのです。
あしや鍼灸接骨院による腱鞘炎の治療方法
腱鞘炎の治療では、安静が重要とされています。そのため、整形外科などでは湿布や痛み止め薬の使用を推奨されることが多いのです。しかし、腱鞘炎は指や手首だけの問題ではないため、これらの対症療法では根本的な解決にはなりません。
あしや鍼灸接骨院では、腱鞘炎の原因に着目した治療をおこなっています。
微弱電流機器「エレサス」
「エレサス」は、体内の生体電流の流れを整える微弱電流機器です。これにより、炎症を鎮め、組織の回復を促進します。つまり、単に安静にするだけでなく、治癒のための基盤を作るのです。
「姿勢」の崩れと体の「ねじれ」に着目して、アプローチ
腱鞘炎の根本的な原因は、姿勢の崩れや体のねじれにあることが少なくありません。これらによって体の使い方が悪くなり、指や手首に過度な負担がかかるのです。
あしや鍼灸接骨院では、姿勢の矯正や体のねじれの調整をおこなうことで、腱鞘炎の根本的な改善を目指します。鍼灸治療なども併用しながら、患者様一人ひとりに合ったアプローチをおこないます。
まとめ
腱鞘炎は、手の使いすぎによって発症する疾患です。指や手首の痛みだけでなく、日常生活にも大きな影響を及ぼします。湿布や安静だけでは根本的な解決にはならないため、早めに適切な治療を受けることが大切です。
あしや鍼灸接骨院では、腱鞘炎の原因に着目し、姿勢の矯正や体のねじれの調整をおこなっています。微弱電流機器「エレサス」も併用しながら、痛みの改善と再発の防止を目指します。
むち打ちは交通事故などで発生する、首や肩周辺の筋肉や靭帯の損傷です。適切な治療をおこなわないと慢性化するリスクもあるため、早期の対処が大切です。
今回は、むち打ちの治療期間の目安や、早く治すための方法、避けるべき行動などを解説します。
むち打ちの治療期間の目安
むち打ちの治療期間は症状の重さによって異なりますが、一般的には症状が軽快するまで通院が必要です。軽症の場合は1ヶ月程度で改善することもありますが、なかには数ヶ月の通院を要したり、慢性化したりするケースもあります。
治療期間を左右するのは、事故の衝撃の大きさや受傷部位、個人の体質などさまざまな要因があります。また、適切な治療を早期に開始することで回復が早まる一方、対処が遅れると治癒が長引く可能性もあるため、注意が必要です。
むち打ちを早く治す方法
むち打ちの治療は「急性期」と「慢性期」の2つの時期に分けられ、それぞれ適切な対処が求められます。
急性期の治療
事故直後から数日間は急性期にあたります。この時期は安静を保ち、患部を冷やすことで炎症を抑えることが大切です。具体的には、アイシングを1日数回おこない、コルセットなどで首の動きを制限し、必要以上に動かさないようにしましょう。
またむち打ちは、事故直後は痛みなどの症状が出ないことも多いため、「大丈夫だろう」と放置せず、早めの受診をおすすめします。症状が出る前から適切な処置をおこなうことで、回復までの期間を大幅に短縮できる可能性があります。
慢性期の治療
事故から数日以上経過した慢性期では、患部を温めて血行を促進させる治療が有効です。ストレッチや軽い運動で筋肉の緊張をほぐし、マッサージで血流を改善することで、症状の回復を早められます。
また、この時期になると痛みも和らいでくるため、徐々に日常生活に復帰していきましょう。ただし、無理はせず、痛みを感じたら休憩を取るなど、身体の声に耳を傾けることが大切です。
むち打ちを早く治すためにやってはいけない行動
むち打ちの回復を妨げる行動もあるので、以下の点に注意しましょう。
| ・患部を無理に動かす:むち打ちの患部は安静が大切です。無理に動かすと症状が悪化するため、医師の指示に従い、適度な安静を保ちましょう。 ・受傷直後に患部を温める:急性期は炎症が起きているため、患部を温めると症状が悪化します。受傷後数日間は冷やすことを優先しましょう。 ・サポーターや湿布を必要以上に使用する:サポーターや湿布は適度に使用することで効果がありますが、必要以上に使用すると筋力が低下したり、皮膚トラブルを引き起こしたりする可能性があります。 ・治療を自己判断で中断する:症状が改善してきたからといって、自己判断で治療を中断するのは危険です。医師の指示に従い、完治するまで治療を継続しましょう。 |
あしや鍼灸接骨院のむち打ち治療
ここでは、あしや鍼灸接骨院によるむち打ち治療を紹介します。
ソフトな施術で痛みなく早期改善を目指す
むち打ちの患部は痛みを伴うことが多いため、あしや鍼灸接骨院では患者様の痛みに配慮した、ソフトな施術を心がけています。 具体的には、軽めの圧でのマッサージや、電気を使った微弱な刺激の施術など、痛みを感じにくい方法で治療をおこないます。 これにより、痛みに敏感な患者様でもリラックスして施術を受けられ、早期の症状改善につながります。
自賠責保険が適用されるので安心して通院可能
交通事故によるむち打ちは、自賠責保険が適用されるため、治療費の心配なく通院いただけます。 あしや鍼灸接骨院では、自賠責保険の適用に関する手続きのサポートもおこなっているため、面倒な書類作成などは一切不要です。 保険適用の条件や範囲については、スタッフが丁寧に説明いたしますので、安心して治療に専念できます。
他の病院や接骨院からの転院・併院が可能
むち打ちの治療は、病院での検査や処置と、接骨院でのリハビリを並行しておこなうのがおすすめです。 あしや鍼灸接骨院では、他の病院や接骨院からの転院や併院も柔軟に受け付けています。 必要に応じて医療機関と連携を取りながら、患者様に最適な治療プランをご提案いたします。
転院や併院に際しての手続きや情報共有も、スムーズにおこなえる体制を整えています。
まとめ
むち打ちは、適切な治療を早期に始めることが大切です。 急性期は安静と冷却、慢性期は温めることを意識し、症状に合わせたアプローチをおこないましょう。 また、むち打ちは、事故直後は痛みなどの症状が出ないことも多いため、早めの受診をおすすめします。症状が出る前から適切な処置をおこなうことで、回復までの期間を大幅に短縮できる可能性があります。
むち打ちでお困りの方は、ぜひあしや鍼灸接骨院への受診をご検討ください。 専門スタッフによる丁寧な施術とアドバイスにより、むち打ちを早期に改善へと導きます。
更年期は、女性ホルモンの変化によってさまざまな症状が現れる時期です。そのなかでも、突然の動悸は不安を感じる症状の一つでしょう。
今回は、更年期に動悸が起こる理由や、その他の症状、対処法について詳しく解説します。また、あしや鍼灸接骨院での更年期障害の治療方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
更年期になると動悸が起こる理由
更年期になると、卵巣の機能が徐々に衰えていき、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が減少します。エストロゲンは、自律神経のバランスを整える働きがあるため、その分泌量の減少は自律神経の乱れを引き起こします。
自律神経は、心拍数や呼吸などの調節に関わっているため、その乱れが動悸や息切れなどの症状として現れるのです。
動悸のほかに更年期に起こる症状
更年期には、動悸以外にもさまざまな症状が現れます。代表的なものとして、以下のような症状があります。
|
・首や肩のこり |
これらの症状は、女性ホルモンの変化によって引き起こされる自律神経の乱れが原因と考えられています。個人差はありますが、多くの女性が何らかの症状を経験するでしょう。
動悸が起きたときの対処法
動悸が起きたときは、以下のような対処法を試してみてください。
| ・深い腹式呼吸を繰り返し、リラックスする ・ラベンダーなどのアロマオイルを使って、心を落ち着ける ・規則正しい生活リズムを心がけ、自律神経のバランスを整える ・カフェインや刺激物の摂取を控える ・ 適度な運動を取り入れ、ストレス解消を図る |
これらの方法は、自律神経のバランスを整えることで、動悸の症状を和らげるのに役立ちます。ただし、症状が強い場合は、医療機関への相談が必要です。
あしや鍼灸接骨院による更年期障害の治療方法
あしや鍼灸接骨院では、更年期障害に悩む女性に対して、鍼灸治療やエレサス、スーパーライザーを用いた独自の施術をおこなっています。これらの治療法は、自律神経のバランスを整えることで、更年期障害の症状改善に効果が期待できます。
鍼灸治療では、身体の状態を細かく診断し、適切なツボに鍼を打つことで、自律神経の乱れを調整していきます。また、エレサスやスーパーライザーといった最新の治療器を用いることで、より効果的に自律神経のバランスを整えることが可能です。
あしや鍼灸接骨院の施術は、東洋医学の知見に基づき、患者様一人ひとりに合わせて乱れた体のバランスを整えていきます。人間には本来、自己治癒力が備わっているため、その力を最大限に引き出すことで、更年期障害の症状を改善へと導くのです。
まとめ
更年期の動悸は、女性ホルモンの変化によって引き起こされる自律神経の乱れが原因です。動悸以外にも、さまざまな更年期症状がありますが、生活習慣の改善や適切な治療によって、それらの症状は改善できる場合があります。
あしや鍼灸接骨院では、鍼灸治療や最新の治療器を用いて、更年期障害に悩む女性を支援しています。更年期の症状でお悩みの方は、ぜひ一度相談してみてください。あなたの症状に合わせた最適な治療プランをご提案いたします。
自律神経失調症に悩む方は多いですが、その症状は人によってさまざまで、診断が難しいことでも知られています。
今回は、自律神経失調症の原因や症状、診断基準について解説します。また、あしや鍼灸接骨院での自律神経失調症の治療方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
自律神経失調症とは
自律神経失調症とは、自律神経のバランスが崩れることで、心身にさまざまな症状が現れる状態を指します。自律神経は、意識しなくても自動的に身体の機能を調節する神経で、交感神経と副交感神経の2つに分けられます。この2つの神経のバランスが崩れると、自律神経失調症を引き起こすのです。
自律神経失調症の原因
自律神経失調症の原因は、不規則な生活習慣やストレス、睡眠不足などが挙げられます。特に、現代社会では多くの方がストレスを抱えており、自律神経のバランスを崩しやすい環境にあります。また、女性ホルモンや甲状腺ホルモンの乱れも、自律神経失調症の原因となることがあります。
自律神経失調症セルフ診断
自律神経失調症の症状は多岐にわたりますが、以下のような症状がある場合は要注意です。
・偏頭痛で薬が手放せない
・「めまい」が頻繁にある
・顎関節症と診断された
・不眠症(夜の寝つきが悪い/朝起きても疲れが取れない)
・頻繁に便秘になる など
これらの症状が長期的に続く場合は、自律神経失調症の可能性も考えられるでしょう。
自律神経失調症の診断基準とは
自律神経失調症の診断基準は、「さまざまな自律神経系の不定愁訴を有し、一方で臨床検査では器質的病変が認められず、かつ顕著な精神障害のないもの」と定義されています。
つまり、自律神経の症状があるものの、検査では特に異常が見られず、明らかな精神疾患もない状態を指します。ただし、自律神経失調症と診断されても、それが他の病気の症状である可能性も考えられるため、注意が必要です。
あしや鍼灸接骨院による自律神経失調症の治療方法
あしや鍼灸接骨院では、自律神経失調症に対して多角的なアプローチをおこなっています。
・磁気を利用した「つむじ風くん」や「陰陽てい鍼」などの刺さない鍼、手動交流磁気治療器「コリンコ」を用いた自律神経の調整
・お灸を使った施術による自律神経のバランス調整と体の巡りの改善
・脈診や触診による体の滞りや異常の発見と的確な鍼治療
・最新の治療器「スーパーライザー」を用いた乱れた自律神経のバランス調整
・骨盤矯正や深層筋調整による体の歪みの改善と自律神経のバランス調整
これらの治療法を組み合わせ、一人ひとりの症状に合わせた治療プランを提供しています。自律神経失調症でお悩みの方は、専門的な治療を受けることで症状の改善が期待できます。
まとめ
自律神経失調症は、現代人に多く見られる症状ですが、その診断は難しいのが現状です。今回紹介した診断基準や症状を参考にすることで、自律神経失調症の可能性を見極められるでしょう。
また、自律神経失調症の治療には、身体のさまざまな部分にアプローチすることが大切です。あしや鍼灸接骨院では、刺さない鍼やお灸、スーパーライザーなど、さまざまな治療法を組み合わせることで、自律神経のバランスを整え、症状の改善を目指しています。
自律神経失調症でお悩みの方は、ぜひあしや鍼灸接骨院にご相談ください。あなたの症状に合わせた最適な治療法をご提案いたします。
スポーツを楽しむうえで、怪我や障害は避けては通れない問題です。特に、繰り返しの動作や過度な負荷によって起こるスポーツ障害は、適切な予防と治療が必要不可欠です。
今回は、スポーツ障害の原因や予防法、治療方法について詳しく解説します。
スポーツ障害とは
スポーツ障害とは、スポーツ活動によって関節や靭帯、腱、骨などに繰り返し外力が加わることで引き起こされる障害のことを指します。オーバーユースや不適切な動作が原因となることが多く、早期の対処が重要となります。
スポーツ障害の原因
スポーツ障害の主な原因は、筋肉への過度な負担や正しい動作の欠如だといわれています。適切な休養を取らずに練習を重ねたり、フォームが崩れたままプレーを続けたりすることで、身体に無理な力がかかり、障害につながります。
スポーツ障害を予防するためには
スポーツ障害を予防するためには、適切なウォームアップとクールダウン、そして無理のない練習が大切です。また、個人の成長段階に合わせたトレーニングも重要なポイントとなります。以下で詳しく見ていきましょう。
準備運動をおこなう
本格的な練習やプレーの前には、必ず準備運動を行いましょう。単にケガ予防だけでなく、パフォーマンスの向上にもつながります。ジョギングやスキップなどの全身運動で体温を上げたあと、動的ストレッチを取り入れるのが効果的です。動的ストレッチとは、関節を動かしながら筋肉を伸ばす方法で、筋肉の柔軟性を高め、関節の可動域を広げられます。
また、実際のプレーで使う動作に近いフォームでおこなう「スポーツ特異的なウォームアップ」も大切です。例えば、サッカーであればドリブルやパス、シュートの動作を取り入れるなど、競技に合わせた準備運動を心がけましょう。
クールダウンをおこなう
練習やプレー後は、ゆっくりとしたペースでジョギングや歩行をおこない、徐々に心拍数を下げていきましょう。その後、練習中に使った筋肉群を中心にストレッチをおこないます。
特に、ハムストリングスや大腿四頭筋、ふくらはぎ、肩周りの筋肉は念入りに伸ばすことが重要です。呼吸を深くしながら、20〜30秒ほど伸ばしましょう。アイシングを取り入れるのもおすすめで、血管を収縮させて炎症を抑える効果があります。
過度な練習は避ける
オーバーユースを防ぐために、練習量は徐々に増やしていくことが大切です。また、練習内容も多様性を持たせ、同じ部位に負担が集中しないよう工夫しましょう。疲労が蓄積しているときは、無理をせず休養を優先することが大切です。
週に1〜2日の完全休養日を設け、十分な睡眠時間を確保しましょう。適切な休養とコンディショニングが、怪我の予防につながります。
個人の発育に合わせた練習をおこなう
成長期の選手は、体格や筋力、発育の度合いに個人差が大きいため、一律の基準でトレーニングをおこなうのは避けましょう。特に、筋力トレーニングは慎重におこなう必要があります。
自重負荷を中心としたメニューを選び、関節の柔軟性を高めるストレッチや、バランス感覚を養うトレーニングを取り入れるのがおすすめです。指導者や保護者は、選手の様子を注意深く観察し、痛みや不調の訴えがあればすぐに対応することが大切です。
あしや鍼灸接骨のスポーツ障害の治療
あしや鍼灸接骨院のスポーツ障害に対する治療の特長は、患者様一人ひとりの身体の状態に合わせた総合的なアプローチにあります。
まず、入念に身体のバランスをチェックし、筋肉や骨格のゆがみを見極めます。そこから、全身のバランスを整えていくことで、痛みの緩和と機能回復を効果的に促進。単に症状の表面的な改善だけでなく、根本的な原因にアプローチすることで、再発のリスクを軽減できます。
また、急性期の怪我には、最新の微弱電流治療器エレサスを用いた施術が威力を発揮します。深部の痛みを取り除きながら炎症を抑えることで、早期の復帰を実現。患者様の状態に合わせて最適な治療プランを立案し、スポーツ復帰までの道のりを手厚くサポートします。
まとめ
スポーツ障害は、予防と早期治療が大切です。正しいウォームアップとクールダウン、無理のない練習を心がけ、症状が出たら速やかに専門家に相談しましょう。
あしや鍼灸接骨院は、豊富な経験と最新の設備で、スポーツ障害に悩む方々を全力でサポートします。1日でも早く、スポーツを楽しめる健康的な身体を取り戻しましょう。
エラ張りで悩んでいる女性も多いのではないでしょうか。エラ張りは、咬筋の発達や骨格の形状により目立ちやすくなってしまいます。そこで、エラ張りの改善に有効なのが小顔矯正です。
本記事では、エラ張りの原因をさらに詳しく見ていくとともに、小顔矯正が効果的な理由について解説します。
エラ張りの原因
エラ張りの主な原因は、次の2つが考えられます。
| ・咬筋が発達している ・骨格の形状 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
咬筋が発達している
咬筋は、頬骨からフェイスラインにかけて存在する咀嚼筋の一つで、頻繁に使うことで筋肉が発達し、エラが張り出すようになります。特に、硬い食べ物をよく食べる方や、無意識に歯を食いしばる癖がある方に見られることが多いとされています。
骨格の形状
個人の骨格、特に顎の骨がもともと大きい場合、エラ張りが目立つことがあります。また、奥歯を食いしばった状態でも咬筋が動かない方は、生まれ持った骨格がエラ張りの原因となっているかもしれません。
エラ張りに小顔矯正が効果的な理由
エラ張りに小顔矯正が効果的な理由は、次の2つが挙げられます。
|
・咬筋のコリが解消できる |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
咬筋のコリが解消できる
咬筋は、頬骨の下から下顎までをつなぐ筋肉で、噛む動作を主に担っています。この筋肉が過度に発達すると顎が前方に突出するため、エラ張りが目立ってしまいます。
小顔矯正では、この咬筋に直接的にアプローチし、筋肉のコリをほぐすことで顎の突出を減少させます。具体的な方法としては、咬筋に圧を加えるマッサージや、特定のポイントを刺激することで筋肉の緊張を和らげ、顔の輪郭を整えます。
これにより、顔全体のバランスを改善し、よりすっきりとした小顔効果が実現可能です。
噛み合わせが改善される
噛み合わせが悪いと咬筋に余分な力がかかり、筋肉が過剰に発達することがあります。小顔矯正では、この咬筋の緊張を和らげ、筋肉のバランスを整えることで顎の位置を正しく調整し、噛み合わせを改善します。噛み合わせが改善されると、咬筋にかかる負担が減少し、エラ張りの予防となります。
あしや鍼灸接骨院の小顔矯正
あしや鍼灸接骨の小顔矯正では、エラ張り解消以外にも次のような悩みを解説します。
| ・肌のハリがなくなりたるんできた ・ほうれい線が気になる ・顔がむくみやすい ・お化粧のノリが悪い ・顔全体の歪みが気になる ・顔色が悪いといわれる ・左右で目の位置や口の形が違う |
あしや鍼灸接骨院の小顔矯正は、全身調整を含めての小顔矯正をおこないます。エステサロンや他店の小顔マッサージや小顔矯正は、顔を揉むことでリンパの流れを改善し、不純物や水分を移動するだけで、結局は元に戻ってしまいます。
あしや鍼灸接骨院の小顔矯正では、根本からの改善になるため、健康にも良いとされています。独自のアプローチ方法で、エラ張りの解消はもちろん、理想の小顔を実現します。
まとめ
本記事では、エラ張りの原因と小顔矯正が効果的な理由について解説しました。エラ張りは、咬筋の発達や骨格の形状により目立ちやすくなってしまいますが、小顔矯正により改善可能です。
あしや鍼灸接骨院では、痛みのない施術で安心して小顔矯正を受けられます。お試し体験も可能なので、エラ張りが気になる方は、ぜひ1度あしや鍼灸接骨院へご相談ください。
頚椎捻挫(むち打ち症)の治療は、一般的には症状が軽快するまで通院することがすすめられます。軽症の場合は約1ヵ月、より重いケースでは数ヵ月の通院が必要となることもあるでしょう。
本記事では、頚椎捻挫(むち打ち症)の治療期間に加え、症状や治療方法について解説します。
頚椎捻挫(むち打ち症)とは
頚椎捻挫(むち打ち症)は、事故により首が強く動かされることで起こる頚椎の損傷です。首にかかる鞭のような動きにより、首の筋肉や靭帯が伸ばされることで、頚椎に痛みや不快感が生じます。
頚椎捻挫(むち打ち症)の症状
頚椎捻挫(むち打ち症)の主な症状には、首を動かしたときの痛みや頭痛、倦怠感があります。これらの症状は、首の筋肉や靭帯が過度に伸びることによって引き起こされます。
また、痛みは首の周囲にとどまらず、場合によっては肩や腕にまで生じることもあるでしょう。日常生活に支障をきたすこともあるため、しっかり治療をおこなう必要があります。
頚椎捻挫(むち打ち症)の治療期間
一般的には、症状が軽快するまで通院することがすすめられますが、治療期間は症状の重さによって異なります。軽症の場合は約1ヵ月で改善することもありますが、より重いケースでは数ヵ月の通院が必要となることもあるでしょう。
症状が慢性化する可能性もあるため、適切な時期に医療機関を受診し、指示に従って治療を続けることが重要です。
あしや鍼灸接骨の頚椎捻挫(むち打ち症)治療
あしや鍼灸接骨の頚椎捻挫(むち打ち症)治療を紹介します。以下で詳しく見ていきましょう。
ソフトな施術で痛みなく早期改善を目指す
治療を継続しても頚椎捻挫(むち打ち症)の症状が改善されない場合、「脳正規髄液減少症」を疑う必要があります。「脳正規髄液減少症」とは、交通事故などにより身体や頭部に強い衝撃を受けることで硬膜を損傷し、髄液が漏れ続け、頭痛や全身にさまざまな不調を引き起こす症状です。
この症状は、電気治療や湿布では治りにくく、ボキボキする手技や揉むだけのマッサージは逆効果になる可能性もあるでしょう。あしや鍼灸接骨院では、頭蓋骨や頚椎、また骨盤に対して優しい刺激でアプローチする方法で治療をおこないます。
体内の約半分といわれる血液やリンパ、そして脳脊髄液などの流れを、特殊な手技施術によって改善します。
自賠責保険が適用されるので安心して通院可能
交通事故治療や後遺症によるリハビリ治療の場合、接骨院でも自賠責保険は適用可能(過失割合による)です。あしや鍼灸接骨院でも自賠責保険が適用されますが、ほとんどの患者様が「窓口負担0円」で治療を受けられております。
さらに、慰謝料や通院にかかる交通費等も保険会社が負担してくれるので、安心して通院できます。
ほかの病院や接骨院からの転院・併院が可能
現在、医療機関(整形外科など)やほかの接骨院・整骨院へ交通事故治療で通院中の方でも、あしや鍼灸接骨院へ転院していただけます。必要な手続きは、あしや鍼灸接骨院で代行するので安心です。
また、医療機関で定期検査が必要な場合でも、あしや鍼灸接骨院と併院が可能です。通勤・通学などで都合が合わないという方も、気軽にご相談ください。
まとめ
本記事では、頚椎捻挫(むち打ち症)の治療期間や症状、治療方法について解説しました。治療期間は症状によって異なりますが、軽症の場合は約1ヵ月、より重いケースでは数ヵ月の通院が必要となることがあります。
あしや鍼灸接骨院の頚椎捻挫(むち打ち症)治療は、ソフトな施術で痛みなく、早期改善します。どこに通っても改善されない頚椎捻挫(むち打ち症)の症状は、ぜひ1度あしや鍼灸接骨院にご相談ください。
膝の内側の痛みの原因は、鵞足炎が考えられるでしょう。鵞足炎は、膝関節の内側から約5cm下に位置する鵞足部に炎症が生じる疾患で、ランナーやアスリート、肥満の方など、膝に定期的な負担がかかりやすい方に見られる傾向にあります。
膝痛は放置してしまうとさらに症状が悪化する可能性があるので、早めの改善が必要です。そこで今回は、膝の内側に痛みがでやすい方の特徴や、治し方について解説します。
膝の内側の痛みの原因「鵞足炎」とは
鵞足炎は、膝関節の内側から約5cm下に位置する鵞足部に炎症が生じる疾患です。鵞足部は複数の筋肉の腱が集まる点で、滑液包炎とも呼ばれます。鵞足炎の症状や原因についてさらに詳しく見ていきましょう。
鵞足炎の症状
鵞足炎の主な症状としては、歩行時や階段の昇り降り、椅子から立ち上がる際に膝の内側に痛みを感じることが挙げられます。この痛みは膝の内側、特に関節から少し下の部分で発生し、活動によって悪化することが多いとされています。
鵞足炎の原因
鵞足炎の原因は、主に歩行やランニングなどで膝から下を外側に捻る動作による繰り返しの負荷が関連しています。特にランナーやアスリート、肥満の方など、膝に定期的な負担がかかりやすい方に見られる傾向にあります。
膝の内側に痛みがでやすい方の特徴
膝の内側に痛みがでやすい方の特徴は次のとおりです。
| ・O脚など姿勢に問題がある ・運動不足である ・肥満である |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
O脚など姿勢に問題がある
O脚の方は、膝の内側に負荷がかかりやすいため、膝、特に内側の痛みを引き起こしやすくなります。膝関節の内側が不均等に圧迫されるため、関節や周辺組織に損傷が生じ、痛みが発生します。改善には適切な姿勢の維持と矯正が必要です。
運動不足である
運動不足になると、脚の筋肉が弱まり、硬直してしまいます。筋肉が十分に機能しないと、膝の安定性が低下し、膝の曲げ伸ばしに必要なサポートが不足するため、痛みが発生します。日ごろから適度な運動を心がけるようにしましょう。
肥満である
体重が増えると、膝にかかる圧力も増大します。特に膝の内側の関節部分に負担が集中しやすくなり、この過剰な負担が関節痛やそのほかの膝の問題を引き起こすことがあります。体重管理と適度な運動を心がけるようにしましょう。
あしや鍼灸接骨院の治療方法
あしや鍼灸接骨院では、膝痛治療において身体のバランスと姿勢の改善に焦点を当てています。膝周辺だけでなく骨盤や股関節を含む広範囲にわたり、筋肉の緊張や凝りを解消し、柔軟性を向上させることを目指しています。
これにより、膝痛の根本的な原因にアプローチし、効果的な痛みの緩和と再発防止を図っています。
まとめ
今回は、膝の内側の痛みの原因と治し方について解説しました。膝痛は、放置してしまうとますます筋力が低下し、さらに症状が悪化してしまいます。そのため、早期の改善が必要です。
あしや鍼灸接骨院の膝痛治療は、周辺の筋肉の緊張や凝り、むくみをほぐし柔軟性を回復させます。筋肉の連動性を意識し膝関節だけではなく、関連性の高い部位にもアプローチして改善を目指します。
どこに行っても治らない膝痛で悩んでいる方は、ぜひ1度あしや鍼灸接骨院へご相談ください。
めまいがひどく、原因がわからず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。めまいの原因はさまざまですが、適切な治療により改善が期待できます。
本記事では、ふわふわしためまいの原因と対処法、治し方について解説します。
ふわふわしためまいの原因
ふわふわしためまいにはさまざまな原因が考えられますが、主に耳や脳の問題やホルモンバランスの乱れ、自律神経の不調が関連しています。耳の内部や脳に異常がある場合、めまいが生じやすくなりますが、脳出血や脳梗塞などの重篤な病状も含まれることがあるため、めまいが頻繁に起こる場合は速やかに受診しましょう。
また、更年期障害や自律神経失調症など、ホルモンのバランスが崩れることによってもめまいは引き起こされることがあります。これらは、全身の血流不良や栄養不足が関与していると考えられます。
ほかにも、スマホやパソコンなどの使用で眼精疲労によりめまいを引き起こしやすくなるため、長時間の使用は避けるようにしましょう。
ふわふわしためまいの対処法
めまいが起こった際の対処法を3つ紹介します。以下で詳しく見ていきましょう。
安静にして水分を摂る
ふわふわするめまいが起こった際は、まず安静にして水分を摂ることが大切です。特に立位での活動中にめまいを感じた場合、転倒のリスクを避けるためにすぐに座るか横になるようにしましょう。脱水がめまいの一因となることもあるため、適量の水分補給を心がけることが効果的です。
目と耳に入る刺激を避ける
めまいの症状を軽減するためには、視覚や聴覚への刺激を最小限に抑えましょう。部屋の明かりを落としたり、音楽を消したり、静かな環境をつくることが大切です。これにより、感覚器官への負担を減らし、めまいを和らげられます。
めまいが続く場合は医療機関を受診する
上記の対処法を試してもめまいが改善しない場合や、めまいが繰り返し発生する場合は、早めに医療機関を受診しましょう。めまいはときに深刻な健康問題の兆候の可能性があるため、専門の診断と治療が必要になります。
自律神経の乱れやホルモンバランスの乱れによるめまいは鍼灸治療が効果的
自律神経の乱れやホルモンバランスの変動によって引き起こされるめまいに対して、鍼灸治療が有効な手段とされています。体内の特定のツボにアプローチし、内臓の機能を調整することで自律神経を整え、全体的な血流を改善します。
この血行促進効果により、めまいを引き起こしやすい血流の悪さを改善でき、結果としてめまいの症状の軽減につながります。
まとめ
本記事では、ふわふわしためまいの原因と対処法、治し方について解説しました。めまいの改善には長期の期間を要する可能性がありますが、治療を継続することで必ず改善されます。
あしや鍼灸接骨院では、緊張性めまい(自律神経の乱れ)と眼精疲労性のめまい(スマホやパソコンでの目の疲れ)に対して対応しております。姿勢や身体の歪み・ねじれに特化した施術をおこなっているので、歪みやねじれを改善しながら筋肉を緩めて血流を促しめまいの改善へと導きます。
どこへ行っても改善されないめまいの悩みは、ぜひ1度あしや鍼灸接骨院へご相談ください。
背中の右側の痛みは、筋肉や骨の問題、内臓疾患、皮膚の問題などの原因が考えられるでしょう。また、普段の姿勢が背中の痛みに影響を与えている可能性も考えられます。
本記事では、背中の右側に痛みがある原因と治療方法について解説します。なかなか改善されない痛みに悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
背中右側の痛みの考えられる原因
背中の右側に痛みが生じる原因として、次の3つが考えられます。
|
・筋肉や骨の問題 |
筋肉痛や骨折、肩甲骨や肋骨の骨折が原因で痛むことがあります。また、右側の肺や腎臓、胆のうの疾患も考えられるでしょう。例えば、肺炎や腎結石、胆のう炎なども右側の背中の痛みを引き起こす可能性があります。
さらに、帯状疱疹のような皮膚疾患も原因の一つです。これらの状態はそれぞれ異なる治療が必要となるため、正確な診断が重要です。
普段の姿勢が影響している可能性も
普段の姿勢が、背中の痛みに影響を与えている可能性も考えられるでしょう。家事や仕事、勉強など、日常生活での姿勢が悪いと背中に大きな負担がかかります。特に、長時間同じ姿勢を続けることは、背中の筋肉を緊張させ、痛みを引き起こす原因となります。
そのため、正しい姿勢に改善することが必要です。定期的に姿勢を意識することや、適切なストレッチ、強化運動を取り入れてみるとよいでしょう。
背中右側の痛みによる影響
背中の痛みがあると、日常生活に大きな影響を与えてしまいます。
| ・下にある物を持つのが辛い ・寝る時も辛く、熟睡できない ・デスクワークで集中できない ・掃除などの家事がやりにくい ・スポーツのパフォーマンスが伸びない など |
痛みが生じた際は、早めに適切な診断と治療を受けることが重要です。早期の対応が回復を早め、日常生活への影響を最小限に抑えます。
あしや鍼灸接骨院の背中の痛みの治療方法
あしや鍼灸接骨の背中の痛みの治療方法について、以下で詳しく紹介します。
微弱電流機器 エレサス
背中に痛みが出ている際は、まずは炎症の消失や組織の回復が不可欠です。早期回復や根本施術を目的に、体に流れている生体電流の流れを整え、症状を治めていく仕組みを作っていきます。
そのため、治すための土台が出来上がっていないまま安静にする方法とでは、全く異なる治り方が実感できるはずです。安静にしていることで一時的に症状は軽減しますが、再発のリスクも高まります。
「姿勢」の崩れと体の「ねじれ」に着目してアプローチ
背中の痛みの場合、背中だけに着目して対処していくことが多いのですが、原因は背中だけではありません。「姿勢」の崩れや体の「ねじれ」によって、体の使い方が悪くなり、背中に過度の負担がかかってしまうケースが考えられます。
そのため、あしや鍼灸接骨院では背中だけではなく、崩れてしまった「姿勢」に着目し、アプローチしていきます。なかなか改善されない背中の痛みでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
今回は、背中の右側に痛みがある原因と治療方法について解説しました。背中の痛みがあると、日常生活に大きな影響を与えてしまうため、早めの治療と改善が求められます。
あしや鍼灸接骨院では、背中にだけ着目するのではなく、崩れてしまった「姿勢」にアプローチしていきます。どこへ行っても変わらない背中の痛みでお悩みの方は、ぜひ一度あしや鍼灸接骨院へご相談ください。
![]()
- 骨盤矯正
- エレサス
- 深層筋調整
- 鍼灸
- 産後骨盤矯正
- マタニティ整体
- メンテナンス
- ART(アクティブ・リリース・テクニック)
- ファシアスリックテクニック(グラストンテクニック)
- 美容鍼
- アトラステクニック
- EMS(インナーマッスル/楽トレ)
- 小顔矯正
- ハイパーナイフ
- スーパーライザー
- 動作改善
- マッサージ
- 整体
![]()
- めまい
- 捻挫
- 肉離れ
- 背中の痛み
- 腰のヘルニア(腰椎椎間板ヘルニア)
- 腰痛・ヘルニア
- 坐骨神経痛
- ぎっくり腰
- 肩こり
- 四十肩
- 五十肩
- 頭痛
- 膝痛
- 自律神経疾患
- 寝違え
- 更年期障害
- メニエール病
- 眼精疲労
- 腰痛(原因不明)
- 首のヘルニア(頸椎椎間板ヘルニア)
- ばね指
- ストレートネック
- 腱鞘炎
- 足底筋膜炎
- 生理痛
- 多汗症
- スポーツ障害・外傷
- むち打ち
- 関節痛



住所:兵庫県芦屋市宮塚町3-4-101
Tel:0797-97-1267